コミケにおいでいただいた方々、お買い上げいただいた方々、誠にありがとうございます。
改めて御礼申し上げます。
コミケで販売した本の、本ブログでの通信販売を開始いたします。
詳細はこちらをご参照ください。
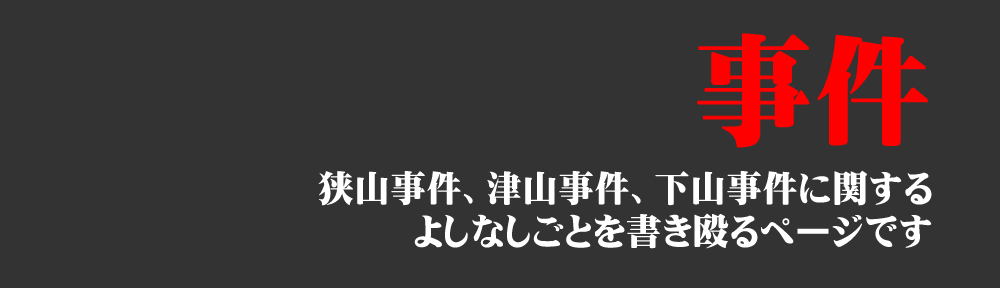
コミケにおいでいただいた方々、お買い上げいただいた方々、誠にありがとうございます。
改めて御礼申し上げます。
コミケで販売した本の、本ブログでの通信販売を開始いたします。
詳細はこちらをご参照ください。
夏コミ最終告知です。
出品予定の本は下記の通りです。なお、今回の新刊の通信販売はコミケ終了後に開始しますので、少々お待ちください。
| 書名 | 著者 | 価格 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 狭山事件 現地インタビュー集 Vol.2 (新刊) | 伊吹隼人 | ¥1,000 | 前回のインタビュー集Vol.1の後の取材結果をまとめたもの。現地住民(被害者元同級生を含む)へのインタビュー等。別冊付録:甲斐仁志氏への反論。A4/46P |
| 下山事件の真実 (新刊) | 事件研究所 | ¥800 | 下山事件に関するまとめ。自殺説が中心になります。本ブログで既に書いたことも一部含みます。A5/60P |
| 津山事件の真実 第三版 付録付き (新刊) | 事件研究所 | ¥3,900 | 津山事件に関する論考を、筑波昭著『津山三十人殺し』の検証を中心にまとめた本。付録: 津山事件報告書(昭和14年、司法省刑事局)。A5/382P(うち付録が248P)。 |
| 狭山事件 現地インタビュー集 Vol.1 | 伊吹隼人 | ¥1,800 | 狭山事件に関連して著者が様々な関係者等にインタビューした内容をまとめたもの。150ページ。インタビュー先についてはこちらをご覧ください。ただし、1)一部の内容は既刊本(『検証・狭山事件』等)と重複しています。2)インタビュー拒否の報告も含まれます |
| 津山事件の真実 第三版 付録なし | 事件研究所 | ¥1,200 | 増補改訂版から付録(津山事件報告書)を除いたもの。考察部分に関しては増補改訂版とほぼ同一ですが、多少の加筆訂正を加えています。A5/130P |
| 狭山事件 – 46年目の現場と証言 | 伊吹隼人 | ¥1,000 | 「伊吹本」オリジナル版(風早書林版)。狭山事件の真犯人推理本の決定版。220ページ (ただし、社会評論社から既に増補改訂版が出ていますので、未読の方はそちらを購入されることをお勧めします。こちらはコレクターズアイテムとしてお考えください) |
本ブログでとりあげている事件に関する同人誌等の通信販売を行っています。詳細はこちらをご参照ください。
コミケで販売する予定の伊吹隼人さんの新刊「狭山事件 現地インタビュー集Vol.2」の概要です。
A4/46P
予価:1,000円
※内容等は若干変更となる可能性もあります。あらかじめご了承ください。
本ブログでとりあげている事件に関する同人誌等の通信販売を行っています。詳細はこちらをご参照ください。
伊吹隼人さん主催の現地調査が無事に終了しました。参加者の方々はお疲れ様でした。以下、当日の模様をフォローアップ含めてお届けします。ここ数年で、特に狭山市駅前が大きく様変わりして事件当時の面影がなくなってしまいましたが、さらに狭山准看護学校も移転したため、さらに再開発が進みそうな感じです。

狭山市駅その1
狭山市駅での様子。

狭山市駅その2
狭山市駅は2010年に橋上駅舎に改装され、事件当時の面影が全く無くなってしまいました。写真の左の方が当日石川さんが休憩したという「荷小屋」の跡地になりますが、今はそれらしい跡はありません。

狭山医師会立准看護学校跡
被害者が通っていた埼玉県立川越高校入間川分校跡地です。跡地は長い間狭山医師会立准看護学校として使用されていましたが、2013年(今年)4月に同校が狭山台に移転して現在は跡地になっています。手前の狭山市中央公民館も既に取り壊されており、奥の狭山市立武道館も建物の耐震問題で2013年(今年)4月から利用停止となっているようです。したがって、この一帯をすべて再開発する予定なのかもしれません。現在ある准看護学校の建物は既に事件後に建て直されたものですが、事件当時を偲ばせる裏口=旧入間川分校の正門門柱の処遇を含めて、今後どうなるか予断を許さない状況です。
入間川分校の沿革についてはこちらのエントリをご参照ください。
 小澤毛糸店跡地付近
小澤毛糸店跡地付近
被害者が当日立ち寄って針刺しを購入した小澤毛糸店はこの辺にあったようです。駅前通りならびに商店街自体が完全に取り壊されてしまったので、当時を偲ぶすべもない状況となっています。
 荒神さま
荒神さま
三柱神社(荒神さま)です。伊吹さんによれば、地主の方の意向でこの神社は残す方向とのことです。ただし、事件当時の境内と比べると数分の一に縮小しています。
 「殺害現場」
「殺害現場」
石川さんの自白による死体発見現場です。今年のニュース等でも登場していました。だいぶ以前から雑木林は姿を消していましたが、周囲を見るとさらに開発が進んでいるようです。
この他にも権現橋(養豚場跡地)から所沢方面に抜ける道路が開通したそうで、刻々と事件当時の面影がなくなっていくことを肌で感じます。
本ブログでとりあげている事件に関する同人誌等の通信販売を行っています。詳細はこちらをご参照ください。
伊吹隼人さんから、1970年代に「狭山市民の会」が現地でかなり突っ込んだ取材、特に、関係者に対する聞き取り調査をしていたとの情報をいただきました。今回の画像は、その「狭山市民の会」(無実の石川一雄さんをとりもどそう狭山市民の会)が編著者となっている本からの引用です。
東京タイムズ記事に関するエントリその2です。今回は、5月7日付のOGに関する記事です。
この記事に関する伊吹さんのコメントは下記の通りです。
一番面白かったのは7日付けのOGに関する記事で、これはどこよりも詳しい内容となっています。
- OGは捜査線上に浮かんでいた
- OG死後、埼玉県警の中刑事部長がOGの遺書を手に記者会見で説明を行った
- OGは婚約者とはしばしば新居でデートするほど仲が良かった
- OGの新居は4月末に完成、5日までには新居の家具を全部運び終わっている
- 新居の建築費用は(OGの)長兄に出してもらった
- 結婚費用に困っており、4月に決まった挙式を5月7日に延期していた
- 事件の日は午後3時頃、新居に寄るのを近所の人が見ている。いつ出たのかは分かっていない
- 死体発見現場付近で自転車のタイヤ跡と地下タビの足跡が発見されており、捜査本部はこれが死体を運ぶ際についたものとみている
- 脅迫状とOGの昭和31・32年度の日記の筆跡には似ている点がかなり認められた
などの記事は他紙では見られないものですし、東京タイムズ記者が相当突っ込んだ取材をしているのは間違いないように思われます。

「(被害者宅)のうら口、台所の窓口に手紙(引用注:脅迫状)がおいてあった」
正月早々に、伊吹隼人さんから「狭山事件に関する東京タイムズの当時の報道が面白い」ということでコピーを送っていただきました。ありがとうございます。読んでみると確かに興味深い記事が多いため、これから何回かに分けてご紹介していきたいと思います。
本日引用したのは、5月4日付の狭山事件発生を報じた第一報です。
伊吹隼人さんから、「区長について その2」エントリへのコメントをいただきました。ただ、コメントとして掲載するには内容が重大すぎると思いますので、新規記事として掲載させていただきます。伊吹さんからも「さまざまな方々のご意見も是非お伺いしてみたい」とのことですので、些細なことでも結構ですのでご意見・ご質問をいただけると幸いです。
なお、下記には今回初公開の内容が含まれています。これらの内容は伊吹さんならびに協力されている方々の取材によって判明した事実に基くものであることを申し添えます。
事件と当時の村内の対立、N家をめぐる事情についてまとめてみました。ここからは果たしてどのような推理が可能になるでしょうか?さまざまな方々のご意見も是非お伺いしてみたいと思っています。宜しくお願いします。(伊吹)
本ブログでとりあげている事件に関する同人誌等の通信販売を行っています。詳細はこちらをご参照ください。また、とらのあな通販もご利用ください。
当方の手違いでしばらくとらのあな通販が在庫切れになっていましたが、復活しました。
「本はほしいが、個人サイトだと個人情報が怖い」という方、銀行振込以外の決済方法をご希望の方はこちらをご利用ください。