続きです。
「狭山事件」カテゴリーアーカイブ
狭山事件: 『46年目の現場と証言』 その2
「狭山事件を推理する」サイトの方で、著者インタビューの第二弾が掲載されています。
前回(インタビュー其の一)と併せて、インタビューの中で明かされている内容と本サイトでこれまで検討してきた内容についていくつかコメントさせていただきます。
狭山事件: 『46年目の現場と証言』
『狭山事件―46年目の現場と証言』という本が2009年早々に出版されることになったとのことです。
「狭山事件を推理する」管理人氏による著者インタビューがサイトの方に掲載されています。このインタビューだけでもいろいろな内容が明かされていますので、興味がある方は是非お読みください。
某「最後の証言」とタイトルは似ていますが(笑)、長年事件に興味を持って調べていた著者が、改めて事件関係者に丹念に取材した結果をまとめた本です。実は、このエントリで書いた「新しい展開」というのはこの本のことでした。ようやく一般に公表できる段階になったということでかなり期待しています。
ちなみに一応書いておきますと、私(当サイト管理人)もこのサイトで狭山事件についていろいろ書いていますが、イヤガラセや脅迫に類することは一切受けたことがありません。メアドもさらしていますし独自ドメインですのでその線から調べればいくらでも私本人にたどり着けると思いますけど。その意味で、下田雄一郎氏がなぜ一切の連絡を絶ってしまわれたのか未だに不思議でもあり、残念なところです。
狭山事件: 石川さんが国連の委員会で証拠開示を訴え
「狭山の風」メルマガによると、狭山事件の容疑者として逮捕され、無期懲役の刑を受けた石川一雄さんが、スイスの国連自由権規約委員会において「日本政府に『証拠開示』をするよう勧告してほしい」という訴えをしたそうです。
石川さんは現在、無期懲役の仮釈放という形で日常生活をしています。刑を終えて自由になっているわけではなく、保護観察下に置かれている上に、今後罰金刑以上の刑罰を受けた場合には無期懲役で刑務所に逆戻りということになります。ご本人の言葉を借りれば「見えない手錠」がついたままの状態ということです。同じ理由でパスポート取得や海外旅行はできないと言われており、石川さんサイドもあきらめていたのですが、今年9月になってパスポート取得が認められ、今回の国連自由権規約委員会への参加という話になったそうです。
これまで何度か触れたように、狭山事件に関して、積み上げると高さ2mにもなる証拠が検察に未開示のまま保管されているとのことで、中には弁護側が何度も開示請求したにも関わらず裁判所と検察が一体となって拒否してきたものもあります。そういった証拠類をすべて開示して欲しいというのが石川さんが今回国連の委員会で訴えたことで、ある意味で日本の司法行政の問題点を浮き彫りにするものです。以前も説明したように、刑札・検察は国民の税金を使って大量の人員を動員し、捜査権を持って証拠集め(時には証拠ねつ造(笑))をしますから、集めた証拠はすべて(弁護側の請求がなくても)開示するのが筋というものでしょう。これに対して弁護側は捜査権も人員も予算もない中で資料集めをしなくてはならないという制約があります。本来は、この証拠集めに関する非対称性を補うのが推定無罪の原則(いわゆる「疑わしきは罰せず」)なのですが、日本においてはそれが守られずにえん罪が生み出され続けているという状況です。
状況はそれとして、このブログ的な本題である狭山事件の真犯人捜しの観点から開示してほしい証拠として、下記のようなものがあります。
狭山事件: 被害者の後頭部の傷
ようやくPCが戻ってきました。まる1ヶ月以上更新が滞ってしまいましたが、今後できるだけ更新していきたいと思っています。
さて、先日殿丘駿星さんのメルマガ「コラム・ゆりかもめ」において、狭山事件被害者の後頭部に残された傷について指摘がありました。とりあえず当該の写真をうpしておきます。上の写真はふつうにスキャンしたもの、下の写真は、頭の上に置いてある目盛りが見えるようにコントラストを上げたものです。この目盛りについて、1目盛りの大きさは明記されていませんが、頭の大きさ(16歳女子なので頭の幅は15~20cm程度でしょう)から考えると一目盛りは1cm、従って傷の大きさは1.5cmというところと思われます。後頭部に1.5cmというのはかなり大きな傷であり、殿岡さんが指摘しているように生前に受けた傷であればここから相当量の血液が出たと思われます。しかし、裁判における弁護側の再三の証拠開示請求にもかかわらず裁判所と検察は「殺害現場」の血液反応検査結果を開示していません。日本で初めてルミノール液による血痕反応の検査が行われたのは昭和24年の下山事件の捜査でしたので(ある意味(笑))、昭和39年の狭山事件当時には当然のように「現場」(「殺害現場」だけでなく、一時的に死体を隠していたという「芋穴」や、その途中の運搬経路とされる農道を含めて)のルミノール検査は行われたはずです。このようなかなり基礎的な事項についても裁判所と検察が証拠開示を行わないという事実が、狭山事件が「暗黒裁判」と言われる一つの大きな要因になっています。
2008年12月23日追記: 後頭部の傷は、公判調書で公表された鑑定書(五十嵐勝爾埼玉県警技師医師作成)によると長さ1.3cm、幅0.4cmとのことです。こちらもご参照ください。
狭山事件: OGの死因
本日の画像は、ブルーバックスの『犯人を追う科学―完全犯罪に挑戦する科学捜査 (1965年)』という本の一節です。この本が出版されたのは昭和40年3月20日ですので、狭山事件が起こった昭和38年から2年足らず、まだ記憶も生々しい時に書かれた本ということになります。また、一審で死刑判決が出た後、二審に入って石川さんが否認に転じた後ということになります。
その死体を検視しただけで死因を農薬中毒と決めたのは、あの当時としては問題であった。死体を外から観察しただけで、農薬中毒の診断を下すことは不可能である。たとえ死体のそばに農薬の容器があったとしても、果たしてそれを飲んだか、また飲んだことが原因で死亡したかということは、死体を解剖検査して、化学的に農薬を検出し得て後に始めて(ママ)可能となる。後に死体の口中を拭った脱脂綿についての検査依頼があって、分析の結果たしかに塩素含有の農薬を証明することはできたが、それだけでは、死因、自殺の線に直接に結びつけるのには無理がある。
しかし実際問題としては犯罪を疑って司法解剖にする根拠はなく、監察医制度の行われていないところだから死因確定のための行政解剖にするわけにもいかない。
まことにごもっともなことですが、根本的な問題として、OGの死因は「溺死」とされていたはずです。この本の著者である渡辺孚氏は事件当時、科学警察研究所科学捜査部長という科学捜査の最前線にいた当事者であったにも関わらず、OGの死因を「農薬中毒」と認識していることになります。このような混乱が発生しているのは解せないところです。
また、最後の方にはこういう記述もあります。
幸いにもその後間もなく真犯人があがったから、その意味では自殺男の解剖はしなくてもよかったといえるようになった。
なってませんってば。きちんと解剖して死因を確認しなかったことで、OGに関する疑惑が白とも黒ともつかないままずっと残ってしまったことを考えると、OGの解剖をしなかったことも刑札の大きな落ち度の一つといえるでしょう。
狭山事件: 洋裁生殺し事件 その3
すいませんまた間が空きました。
「洋裁生殺し」の概要ならびに狭山事件との関連性については、以下の記事も参照してください。
今回の画像は、事件が起こった地元の北海道新聞で、犯人が妻と心中した直後に出た記事です。
狭山事件入門: TN
狭山事件において、2番目の変死者が5月11日に「自殺」したTN(当時31歳、狭山市柏原新田在住)です。
TNの「自殺」の状況は下記の通りです。
- 5月11日午後8時すぎ、台所で夕食の後片付けをしていた奥さんがうめき声がするので奥の間に行ってみると、TNが鶏を殺す時に使う刃先が三角形にとがったナイフで胸を一突きにしてうつ伏せになって死んでいた
- TNのすぐ横にはもうすぐ2歳になる子供が眠っていた
- 隣の部屋ではTNの父が茶を飲みながらテレビを見ていた
- ナイフはもともと台所にあったもので、奥さんはいつ持ち出したか気がつかなかった
- 通常、刃物で自殺する際にはためらい傷が見られることが多いが、そのようなためらい傷は一切なかった
- 胸を刺す際にはナイフをうまく横にして入れなければ肋骨に引っかかってしまって心臓まで刺さらないが、一突きで心臓を刺し貫いていた。
- 新聞には、刑札の捜査結果として「市議選問題でさる1日ごろから悩み神経衰弱気味だった」と書かれたが、家族の証言ではそのように選挙に深入りしていたことはなかった
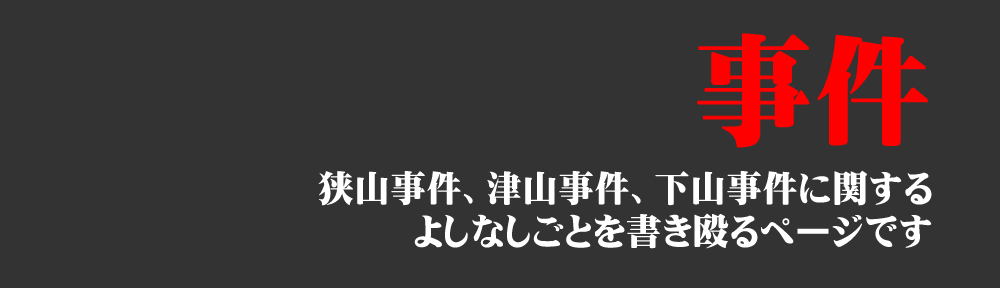
 被害者の後頭部の写真 『狭山事件公判調書 第二審』より
被害者の後頭部の写真 『狭山事件公判調書 第二審』より 被害者後頭部その2
被害者後頭部その2 『犯人を追う科学-完全犯罪に挑戦する科学捜査』
『犯人を追う科学-完全犯罪に挑戦する科学捜査』 北海道新聞 昭和37年11月22日付
北海道新聞 昭和37年11月22日付 朝日新聞 昭和38年5月13日付朝刊
朝日新聞 昭和38年5月13日付朝刊 埼玉新聞昭和38年5月7日付朝刊
埼玉新聞昭和38年5月7日付朝刊